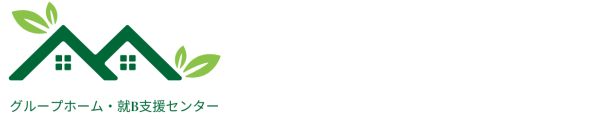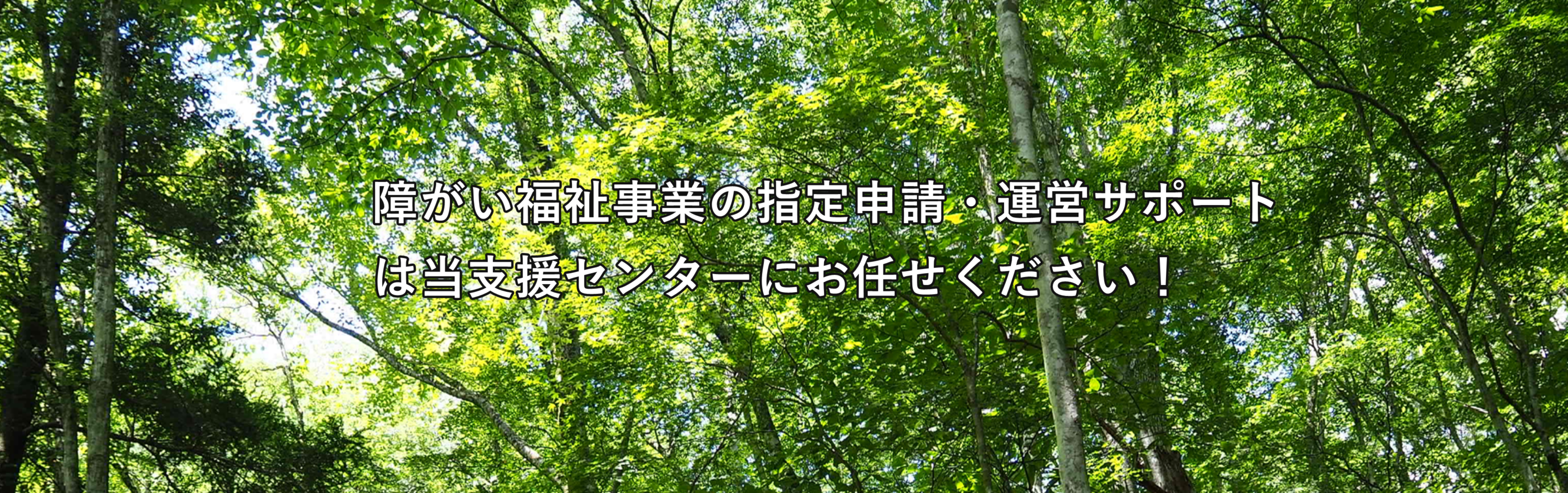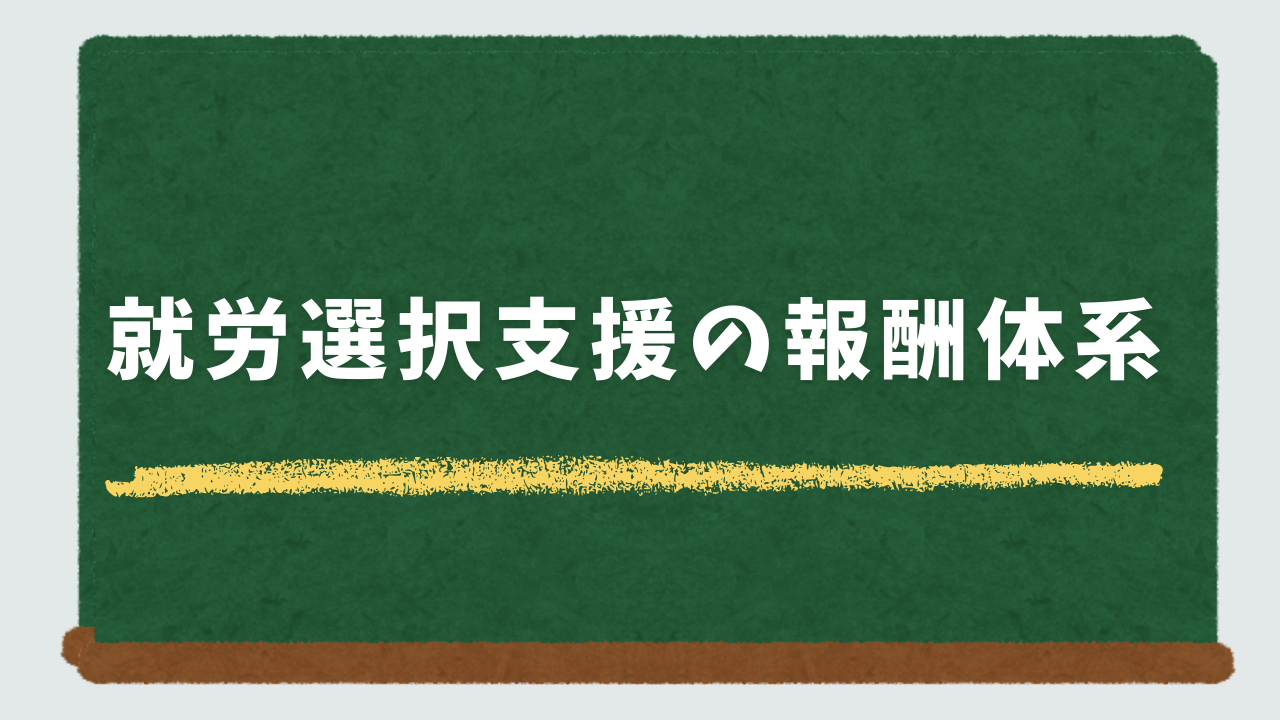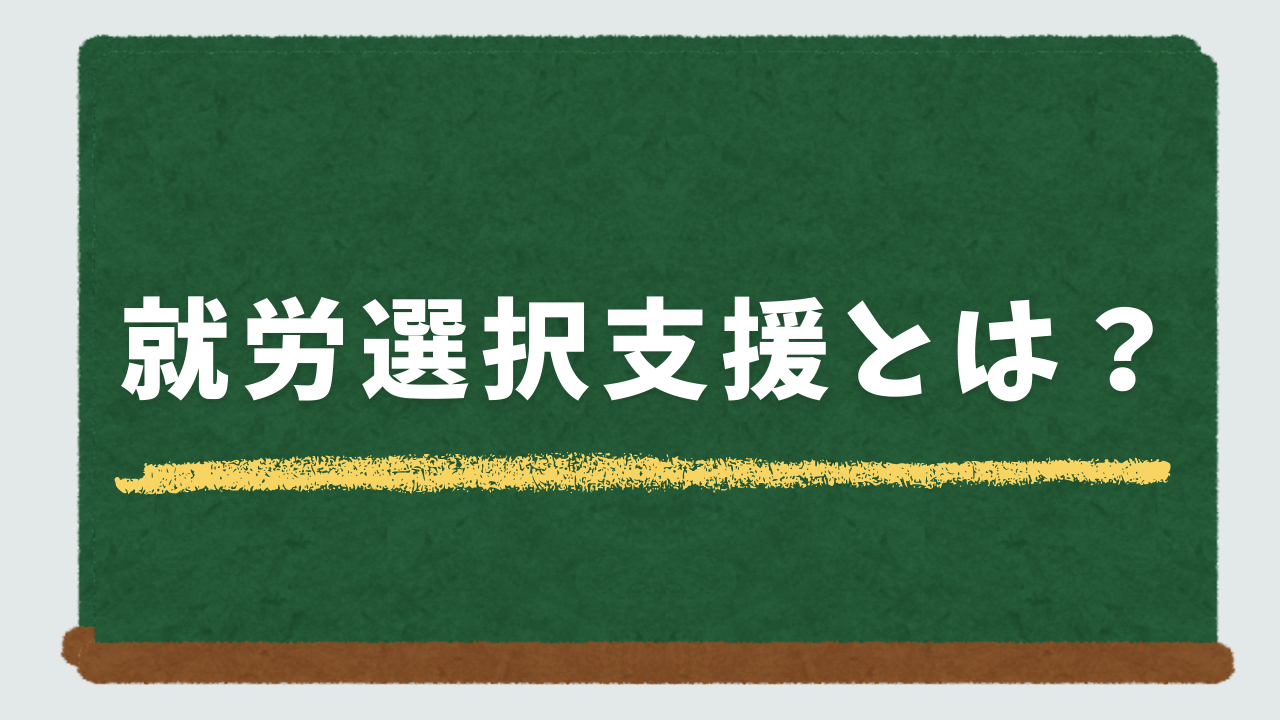
就労選択支援とは?
令和4年に障がい者総合支援法が改正され、障がい者本人の希望や就労能力・適性に合った就労先や働き方を選択できるよう支援する「就労選択支援」が創設されました。この新たなサービスは、就労アセスメントの手法を活用し、個々の強みや課題を整理しながら適切な就労機会を提供することを目的としており、施行は令和7年10月を予定しています。
就労選択支援の支援内容
- 短期間の生産活動等を通じて、利用者の就労適性・知識・能力を評価し、就労に関する意向の整理(アセスメント)を実施。
- アセスメント結果の作成にあたり、利用者および関係機関の担当者を招集し、多機関によるケース会議を開催。利用者の就労に関する意向を確認するとともに、担当者からの意見聴取を行う。
- アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関との連絡調整を実施。
- 協議会への参加等を通じて、地域の就労支援に関する社会資源や雇用事例等の情報を収集し、利用者の進路選択に役立つ情報提供を行う。
就労選択支援の対象者
- 就労移行支援または就労継続支援の利用を希望する者
- すでに就労移行支援または就労継続支援を利用している者
就労継続支援B型の利用要件
令和7年10月より、就労継続支援B型の対象者は次のとおり変更されます。
「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」
このため、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合、事前に就労選択支援を利用する必要があります。
ただし、以下の者については、アセスメントなしで就労継続支援B型を利用できます。
- 50歳に達している者
- 障がい基礎年金1級受給者
- 就労経験があり、年齢や体力面で一般企業への雇用が困難な者
例外措置
以下の状況では、就労移行支援事業所等によるアセスメントを経ることで、就労継続支援B型の利用が認められます。
- 最寄りの就労選択支援事業所への通所が困難である、または近隣に事業所がない場合
- 利用可能な就労選択支援事業所が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
就労選択支援を利用できる対象者
障がい者本人の希望に応じ、以下の者は就労選択支援を利用することが可能です。
- 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある者
- 以下のいずれかに該当し、新たに就労継続支援B型の利用を希望する者
- 就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業への雇用が困難となった者
- 50歳に達している者
- 障がい基礎年金1級受給者
- すでに就労移行支援または就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等を希望する者
就労選択支援事業者の実施主体
就労選択支援事業者の実施主体は、以下の条件を満たす事業者と定められています。
- 就労移行支援または就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であること
- 過去3年以内に、当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績があること(要件①)
- または、これと同等の障がい者への就労支援の経験・実績を有すると都道府県知事が認める事業者であること(要件②)
地域の実情を考慮した対応
一部の地域では、「過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された事業者」(要件①)を満たす事業者が存在しない場合があります。そのため、都道府県知事が認めるその他の同等の就労支援の経験・実績を有する事業者(要件②)も、実施主体として認められます。
要件②の該当例として、以下のような事業者が想定されています。
- 障がい者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障がい者能力開発助成金を活用した障がい者能力開発訓練事業を行う機関
- 要件①を満たす事業者と同等の実績を持つ事業者
市区町村内に事業所がない場合の対応
同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合、例えば以下の条件を満たす事業者も対象となることが考えられます。
- 過去10年間の連続する3年間において、合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された事業者
人員基準
従業者(就労選択支援員)
常勤換算で利用者÷15以上
管理者
原則として、管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
就労選択支援員の兼務について
一体的に運営される就労移行支援事業所等の常勤の職業指導員等について、直接処遇に係る職員は、利用者へのサービス提供に支障がない場合に限り、就労選択支援員として従事することが可能です。また、兼務する勤務時間は、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することができます。
就労選択支援員の要件
就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とします。
ただし、経過措置として、令和9年度末までは、厚生労働大臣が定める研修を修了した者も就労選択支援員として認められます。(令和7年厚生労働省告示第89号による規定)
この研修には、障がい者の就労支援に関する基礎的知識やスキルを身につける内容が含まれます。該当する研修は、以下のいずれかです。
基礎的研修と同等以上の研修
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
※各研修の法的根拠については、厚生労働省告示や関連法令に基づきます。
就労選択支援員養成研修の受講要件
就労選択支援員養成研修を受講するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 基礎的研修を修了していること
- 障がい者の就労支援分野において通算5年以上の勤務実績があること
ただし、令和9年度末までは、基礎的研修または同等以上の研修を修了した者も、養成研修の受講が可能です。
「障がい者の就労支援分野の勤務実績」とは?
以下の職種における勤務経験を指します。
- 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所の管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員、就労定着支援員
- 障がい者職業センターの職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在籍型を除く)
- 障がい者就業・生活支援センターの生活支援担当者、就業支援担当者
- 障がい者職業能力開発助成金による訓練機関の就職支援責任者、訓練担当者
- 令和9年度末までに基礎的研修または同等以上の研修を修了し、就労選択支援員として勤務した経験がある者
設備基準
訓練・作業室
訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室
間仕切り等を設けること
洗面所・便所
利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備
報酬
就労選択支援の報酬は、事業者が提供するサービスの内容や体制に応じて決定されるもので、基本報酬と加算・減算によって構成されます。
基本報酬
就労選択サービス費 1210単位
利用者に対して短期間の生産活動等を通じたアセスメントを実施し、適性や希望を整理する支援を行うことが前提となります。
加算
加算は事業所の支援体制や利用者の状況に応じて報酬が増額される仕組みで、就労選択支援の加算には、次のようなものがあります。
- 福祉専門職員配置等加算
- 視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算
- 高次脳機能障がい者支援体制加算
- 欠席時対応加算(月4回を限度)
- 医療連携体制加算
- 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
- 食事提供体制加算
- 送迎加算
- 在宅時生活支援サービス加算
- 緊急時受入加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
減算
減算は、事業所の運営体制や支援の適正性に問題がある場合に適用され、報酬が減額される仕組みです。就労選択支援の減算には、次のようなものがあります。
- 定員超過利用減算
- 人員欠如減算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 特定事業所集中減算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 虐待防止措置未実施減算
- 業務継続計画未策定減算
- 情報公表未報告減算
まとめ
障害者総合支援法の改正により創設された就労選択支援は、個々の適性を踏まえた職場選択を支援する仕組みです。短期間の生産活動を通じたアセスメントや関係機関との連携を通じ、障がい者の就労課題を整理し、適切な支援を提供します。令和7年10月の施行後は、就労継続支援B型の利用要件にアセスメントの実施が含まれ、新たな基準のもとで運用されます。地域の状況に応じた対応も考慮され、幅広い支援体制が整備される予定です。